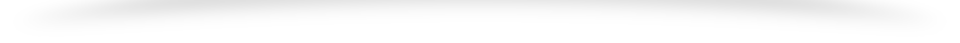JR広島駅の新しい駅ビルと一体となり、広島駅から稲荷町電停の間を短絡する「駅前大橋ルート」が、
2025年8月3日に開業しました!
3月24日の駅ビル「minamoa(ミナモア)」開業に続き、のりばや軌道、運行設備の整備が進められてきた新路線。
6月頃からは試運転も始まりました。
注目度も高く多くの利用者、ファンが待ち望んだ駅前大橋ルート。
開業当日の早朝、一番列車が走り出す歴史的瞬間を見届け、早速乗車してきました!
生まれ変わった広島の玄関口の様子をレポートします!
朔日更新した、広島駅ビル内の新しいのりばに続き、
実際に乗車して稲荷町、松川町を目指します。
前回、新ルート開業で廃止となる区間の最後の状況です。
目次
広島駅出発進行!高架から市街地方面に下り降りる駅前通り
ミナモアの大階段から、今回の開業区間を見下ろしました。
試運転ではなく本当の営業列車がここを走っているのが感慨深い…
地上から。
  |
  |
交差点上空は橋梁、そこから駅前大橋までは軽量盛土区間です。
走行音は非常に静かで新しい車両であれば走行しているのが気づかないほどだったかと思います。
乗車した際の車窓です。
いつも見ている馴染のある建物ですが、角度が変わるだけで非常に新鮮です。
駅前大橋を下り地上に戻る車両たち。
駅前大橋部分が、最急勾配4%の付いた区間です。
広島駅出発後は信号待ちをせずそのまま稲荷町までノンストップで行ってもらいたかったですが、
乗車した車両も含め、信号待ちをするケースが多かったです。
ここは発車時刻を連動させていると思っていたのですが、この日はうまくいかなかったのか、
それとも、そもそも運次第でそこまで考慮していないのか…。
駅前大橋南詰交差点から稲荷町方面。
これが新しい広島の風景です。
全長66mの大型タイプも!4方面の稲荷町電停
広島駅を出発して最初の前提「稲荷町」に到着しました。
この稲荷町電停(下り)は、全長が約66m。5連接の超低床車両が2。編成同時に停車・乗降できる長さを持っています。
自動車交通量の多い交差点で、本線と比治山線を効率よく捌くため設備です。
ちなみに、2枚目の画像の5200形には、駅前大橋線開業を祝うラッピングが施されています。
京三製作所は鉄道の信号システムを担う会社です。実際に本プロジェクトでシステム開発等を担ったのでしょうね。
【京三製作所】:広島電鉄(株)で期間限定の広告ラッピング電車が運行されています! (454KB)
広島駅方面を振り返ります。
開業したものの軌道はまだバラストがむき出しで舗装されていない状態が続きます。
当面、この状態で営業し路盤が安定したところでコンクリートの蓋をするそうです。
電停壁面には試運転時には見られなかった、全く新しいサインが設置されています。
後述する松川町電停でも同様の表記がされており、方面別でAとB(稲荷町電停の場合はAーD)の電停記号が付与されるようです。
稲荷町交差点を行き交う路面電車。
これまでは東西に直進する方向での運行でしたが、これからは相生通りに右折して紙屋町方面に向かうこととなります。
交通量が多い交差点なので、当然直進現示では紙屋町方面の列車は出発できません。(直進する5号線広島港行きは出発可能)
逆の広島駅方面も同様で、ここでの時間ロスが目立ちました。
こちらは紙屋町・八丁堀方面の列車が停車する上りの電停です。
開業前から新しい上屋での運用が始まっています。
電停記号「A」は同様に開業直前に設置されました。
ちなみに新ルートの供用で使用を休止した旧本線下りホーム。
2026年春から運行を始める循環ルートで再び使用される予定です。
それに合わせて今後上屋の更新も行われるものと思われます。Cホームになると思われます。
駅前通りに新設 比治山線内の稲荷町電停
このまま駅前通りを直進し、比治山線の新ルートを進みます。
こちらは先程の稲荷町交差点に面する、比治山線内の稲荷町電停です。
  |
  |
上屋は、A・Bホームと同様のデザインとなっています。
5連接車両が1編成止まれるよう30m程度の全長かと思います。
電停から、先の松川町方面。
かなり近くに、松川町電停が確認できます。
43年ぶりの新設電停 比治山線『松川町』
稲荷町と比治山下電停の中間に、松川町電停が開業しました。
広電では南区役所前以来43年ぶりとなる新設電停です。
駅前通りと市道が分かれる松川町交差点に設置されています。
先程の稲荷町電停と全面ガラス張りの背板は共通ですが、上屋の形状が異なります。
開放的かつシックで非常に美しいです。
ここからは片側1車線の市道となり、従来の比治山線に合流します。
開業直後の新ルートに乗車した感想
まだまだ課題は山積みであると感じました…。
従来の遠回りルートを改め、さらに交差点を一つ高架で乗り越えることで所要時間の短縮を目指した本ルートですが、
現状はなかなかスムーズにいかない場面が多いです。
特に、高架から地上へ降りた直後の「駅前大橋南詰」交差点では早速信号に引っかかることが多く、スムーズな走行が実現されていない印象です。
また、利用者の多さにより、広島駅をはじめとした主要停では乗降に時間がかかり、結果としてダイヤの乱れが頻発していました。
広島駅の発車タイミングが理想通りにいかず、出発後すぐの交差点で再度停車することで、さらに遅延が広がるという悪循環にも陥っているのではないかと思います。
また、新しい広島駅では降車専用ホームを設けて動線を分離する設計でしたが、初日は途中からその運用がなぜか停止されました。何らかの理由があったとは思われますが、混雑対策としては致命的なマイナスポイント。
乗車ホームに三つの路線の乗降客が集中する形となったことにより混雑が激化し、乗降にかかる時間も延びていたように思います。


行先別にのりばを固定する運用は分かりやすさの面では有効ですが、こうしたダイヤ乱れの際の柔軟な運行を妨げる可能性もあります。
のりばを臨機応変に運用するなど、今後はより機動的な対応が求められます。
SNS上では、広島駅の手前に降車専用の電停を設けてはどうかとか、旧来のような職員による目視でのポイント制御を復活させてはどうかという意見も見られました。
気持ちは分かります…が、路面電車の円滑化と高度化を目指してこれまで積み重ねてきた努力を後退させることになるので、調整と技術開発を待ちつつ、もう少し堪えてあげましょうや…(^_^;
それよりも最大のボトルネックであると感じたのは、稲荷町交差点でした。
従来ルートでは直進で通過していた交差点ですが、新ルートではここを右折する必要があるため、交通量の多いこの交差点では、右折矢印信号の出るタイミングでしか通過できません。
一度の信号現示で通過できるのは1編成のみであり、信号サイクルが約120~150秒であることを考えると、通過効率は極めて低い状況です。
広島駅行きについても同様に右折扱いとなるため、現行の信号制御では輸送力確保が難しくなっています。
公共交通に優しい信号現示の再検討は急務です。警察との連携や事前検証を十分に行えなかった広島電鉄にも改善の余地があると感じました。
とはいえ、警察としては自動車の交通渋滞を招く原因ともなりかねないので、調整は容易ではないことは承知しています。
結局のところ、路面電車の運行体系を大きく改善しても、街中に流入する自動車の総量を減らすハード面の対策や、ソフト面(モビリティマネジメント)の対策がなければ、得られる効果は限定的であることが露呈した形ですね。
これは広島電鉄だけではなく、行政の課題でもあります。
新ルートでは、開業初日に広島駅でのポイント故障、2日目に稲荷町で発生した信号トラブルが発生しました。
全く新しいルートであり難しさは理解できますし、まだ初期トラブルの段階である今だからこそ、「仕方がない」で済んでいるうちに、原因の検証と再発防止策を徹底していただきたいと感じます。今後の運行に支障を来さないためにも、早急な対応が必要です。
課題は多いものの、これまで制約だらけだった既存ルートに比べて、新ルートには大きな可能性があることも事実です。
今後の改善を通じて、この新ルートが都市の足としてふさわしい基幹公共交通へと進化していくことを強く期待しています。