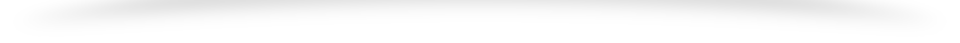広島電鉄は、2018年3月末の完了を目指し、路面電車「広電本社前」電停の大幅リニューアルを進めています。
電車が2編成同時に停車できるよう長さを54mに延ばすほか、
終端駅以外ではこれまでに例のない3mの電停幅を確保し、広電の電停としては初めて待合室も設けられる予定です。
将来的には路線バスも乗り入れ、同じ電停で発着・乗り換えできる仕組みも検討される先駆的な電停になります。
前回の状況です。
広島電鉄からリリースがあり、リニューアル電停は3月28日(水)から供用開始となることが分かりました。
【広島電鉄】:「広電本社前電停リニューアル記念乗車券」の発売について
将来の路面電車-バスの乗り換えも見据え、待合室には冷暖房も完備されているようです。
1月末に訪れて、1ヶ月以上が空きました。
現在の電停はこのような状況になっています!
古い電停はすでに撤去され、拡張された電停全体に上屋が堂々と姿を表しています!
連接車が2編成同時に停車できる、全長54mの新電停です。
広電本社ビルとは反対側となる西側の歩道から。
電停には以前までもう少し北側(紙屋町方面)から出入りしていましたが、リニューアルに伴いこの交差点近くに横断歩道もろとも移設されました。
写真では伝わりにくいですが、従来のリニューアル電停と比べ、やはり上屋が高いのがかなり新鮮に感じます。
電停の端には新しい発車案内装置が取り付けられていました!
大型の電停に合わせ、この装置も従来より大きい新型です!
これまでの電停に取り付けられているものはフルカラーのLEDタイプですが、
こちらはどうやらLCD(液晶モニター)になっているようです。
この電停は将来的に路線バスも乗り入れる計画となっているため、
バスのロケーションシステムも統合して柔軟に表示できるようにするため、LCDになったのでしょう。
電停の中央付近から振り返ります。
待合室はまだ整備中といったところです。通常の電停に待合室が設けられるのももちろん初めてです。
冷暖房も完備し快適に電車を待つことができるようになります。
冒頭に書いたように、従来の古い電停は完全に撤去され、本設の電停が延長されました。
延長部はまだ使われていませんが、2編成同時に入線してもかなり余裕があるのがすでに分かります。
紙屋町側にも案内装置を取り付けるための鉄骨が設けられています。
現在は元々付いていた小型のLED装置を取り付けていますが、こちらも大型LCDに置き換えられるのでしょうか。
大型電停にリニューアルされる「広電本社前」電停。
待合室や電停延長部分など、全ての供用開始は3月28日(水)の予定です。
ちなみに今の電停と重なる区間にあった「広電前」の宇品方面バス停は、昨年12月18日に100mほど北側に移設されました。
移設前は鉄骨とガラスの新しい停留所でした。
電停内に乗り入れるようになるまでの措置と思われますが、このタイプのバス停ってまだ作っていたのですね…。