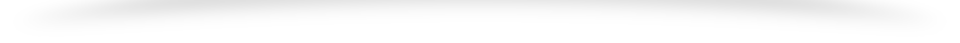ツイッター内にて教えていただきました。ありがとうございます。
広島電鉄は9月26日付で新たな商標を登録しているようです。その商標というのが、
Greenmoverlex
というもの!
[商願2013-74897] 商標:Greenmoverlex / 出願人:広島電鉄株式会社 / 出願日:2013年9月26日 / 区分:14(キーホルダーほか),16(文房具類ほか),24(布製身の回り品),39(鉄道による輸送)
— 商標速報bot (@trademark_bot) October 24, 2013
広島電鉄は今年2月に初投入した1000形を新たに3編成、今年度中にも増備することを予定しています。
1001号はピッコロ、1002号はピッコラという愛称が付きましたが、
もしかすると1003号以降はグリーンムーバーlexという愛称で統一されてしまうのかもしれませんね。
“Green”と付くからには従来通り緑色ベースの車両になるのでしょう。
以前にも書きましたが、私は非常にピッコロ・ピッコラのマルーン色、あの深い赤紫の色が気に入っています。
この2編成限りにもしなってしまうのだとしたら個人的に本当に惜しいです。。

商標登録ついでにもう2つ、今年広電はこんな商標も出願していました。
[商願2013-42437] 商標:http://t.co/gNBqsKet36 / 出願人:広島電鉄株式会社 / 出願日:2013年6月4日 / 区分:35(広告業ほか),36(預金の受入れ及び定期積金の受入れほか),37(建設工事ほか),39(鉄道による輸送ほか),41(当…
— 商標速報bot (@trademark_bot) July 1, 2013
[商願2013-42438] 商標:http://t.co/PPOtKdeqnj / 出願人:広島電鉄株式会社 / 出願日:2013年6月4日 / 区分:35(広告業ほか),36(預金の受入れ及び定期積金の受入れほか),37(建設工事ほか),39(鉄道による輸送ほか),41(当…
— 商標速報bot (@trademark_bot) July 1, 2013
今年6月、これら2つのロゴマーク(?)が出願されていたようです。
これまでマークと漢字のロゴマークからは想像もつかないほど奇抜ですねw。
こちらのように今年6月に申請されたにもかかわらず未だに使われていないものもあるのです。
「Gleenmover lex」もひょっとすると将来の5連接新型低床車で使う名前として今から申請しておいたもの、
と解釈できないこともないということです。
まあ私の中の悪あがき的な捉え方です(笑)
もう10月も終わります。
3連接車の追加投入を待ちたいですね。