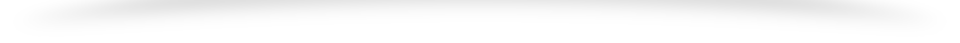またまたこのタイトルで記事を書いてみます。
過去のシリーズはこちら。
広電のLRT化に向けて 胡町・八丁堀電停統合の提案
広電のLRT化に向けて 『急ぐ時はバス』?
今回は「サイドリザベーション」および「センターリザベーション」の提案です。
言うまでもなくヨーロッパは路面電車が早くから見直され今ではLRT先進国(地域)となっていますが、
広電のLRT化においてサイド/センターリザベーションは大いに参考にすべき点の一つだと思っています。
サイド/センターリザベーションとは、路面電車の軌道敷を道路の歩道脇(サイド)または中央(センター)に
車道とは分離して敷設することを言います。
分離には各路線で違いますが、植え込みや段差などが用いられるのが一般的です。
自動車の干渉を受けづらくすることで路面電車の速達性や定時性が向上します。
ということでまずは海外の例を紹介してみたいと思います。
確か以前も紹介したことがありますが、フランスの首都パリを走るトラムの動画です。
論点がずれないよう予め書いておくと、今回見ていただきたいのは軌道と車道を如何にして分離しているかというところです。
大規模な芝生軌道や広々とした電停を紙屋町に作るのかということははまた別の話ですね。
軌道と車道が境界ブロックや芝生、歩道、さらには植樹など様々なパターンの分離の仕方があるものですね。
動画中の4分頃には車道のセンターを走っていた軌道がサイドへ移り変わる様子なども分かります。
広島は市内線はほとんどの沿線で車の交通量が多いです。
右折待ちの車が軌道に接近し安全確保のために電車が速度を落とす、運が悪いと一時停止して車の通過を待つ間に信号が赤になり交差点を通過出来ないという場面を何度も見ています。
センターリザベーション化で今より少しだけ車道と軌道の間隔を空け、段差も付けることでかなりそれは改善されると思います。
右折待機位置の修正です。

もちろんそれに合わせて右折車を電車通過時のみ一時的に制限するような優先信号の構築も必要ですね。
車道と軌道の間のスペースに架線柱や信号を設置すれば、電線だらけの現状から景観も良くなり理想的です。
実は広島電鉄でもほんの一部の区間では“サイドリザベーション”に関しては実現されています。
宇品線の海岸通~広島港の区間です。ファンでなくともご存知の方も多いと思います。

(2008年6月撮影)
広島港電停の移設や広島高速3号線建設に合わせて整備されたものですね。
ここは高速道路の高架があり道路幅の感覚が分かりにくいのでこちらも。
元宇品口~広島港間の南北の線路です。



元々自動車の交通量が少ない区間ではありますが、比較スムーズに電車が運行できているように感じます。
広島において”サイド”リザベーションが適しているだろうなという場所が平和大通りです。
特に西観音町~[平和大通り]~土橋間のクランク解消を目的とした延伸が望まれている区間です。
少し前にこの可能性を検討する意味も込めて歩いてみました。





(全て2013年7月撮影)
ずばり緑地帯を使います。
サイドと言っても道路の南北どちら側に寄せるのか、電車の上下線を分割するのか、通りの象徴の緑地帯を無くしてしまうのか
という部分でまだまだ議論・検討はなされるべきだと思います。
個人的には西観音町から上下線を分割しないまま南北どちらかの緑地帯へサイドリザベーション化するのが一番良いと思います。
この広電平和大橋線構想(江波線以西)で最も課題となるのが、天満川を越える緑大橋の老朽化・強度不足です。
従来通り路面電車を通すなら橋の架け替えが必要でここに多額の費用が掛かるため二の足を踏んでいると言われています。
ならば平和大橋を参考にしましょう。
平和大橋歩道橋は2017年度に。欄干も復元へ。
平和公園の東側、元安川に掛かる平和大橋を快適に歩行者が渡れるようにするため
平和大橋の南北両側に歩行者専用橋を新設する事業です。
(17年度に暫定的に北側が完成します。)
これまで歩道だったスペースは車道に拡幅されるため自動車にとっても安全が確保される効果があります。
平和大橋そのものを掛け替えるより安価で通行止めもすることなく実現させることができます。
サイドリザベーション化するにあたって緑大橋は歩道と路面電車の軌道を備えた橋を新設すれば架け替えを必要とせず、
比較的低予算で平和大通り線を実現できるのではないかというのが私の考えです。
ところが、以前広電側からこのサイドリザベーション案を提案するも、
結局却下され従来通り中央に敷設する案が構想段階ながら採用されたという経緯があります。
(コメントで教えていただきました。ありがとうございます。)
当時は90年代後半です。路面電車を取り巻く時代背景は大きく変わっているはずですから
広島の都市交通全体を見直す中でもう一度提案・検討していただきたいです。
サイド化すれば歩道から直接電車に乗れるような感覚になり、歩行者との親和性が高い所もメリットです。
一方でセンターリザベーションが適している場所はやはり市中心部の既存路線だと思います。
費用対効果を考えると最も交通量の多い広島駅~紙屋町付近までの相生通り、そして鯉城通りに限定したほうが良いですね。

こういった新しい試みは一見困難に見えますが
実際に熊本県の熊本市交通局は熊本駅~田崎橋間の約570mもの区間でサイドリザベーション化されました。
【公営交通事業協会】:熊本市電サイドリザベーションの取り組み(PDF, 約630KB)
札幌市においても札幌市電のすすきの~西4丁目間を接続しループ化するにあたり、
サイドリザベーション方式が採用されました。(しかも制振軌道だそうで)
【国土交通省】:札幌市軌道運送高度化実施計画の概要(PDF, 約340KB)
これまでと同じように線路を敷くより大幅にコスト増にはなりますが、
新交通や地下鉄を新たに建設するよりは遥かに安価ですし、国の路面電車に対する見方も大きく変わってきています。
広島120万都市に相応しい市民の足となるためにあらゆる可能性を検討していただきたく思います。